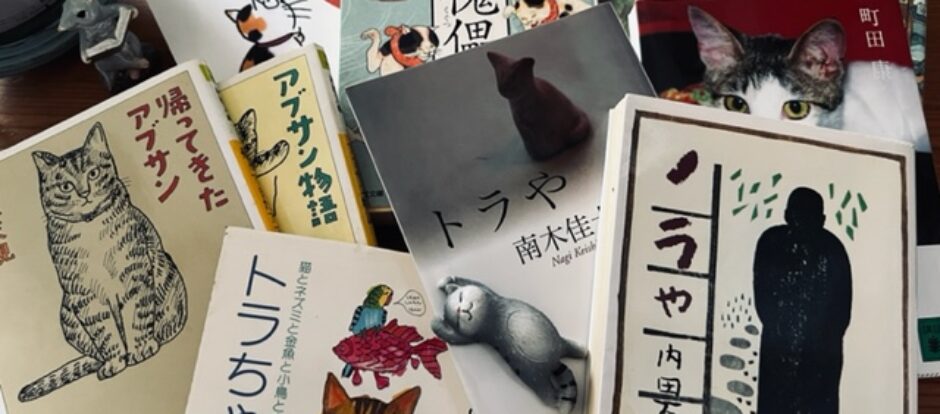【乱読雑記】
もう少し素敵な小説かエッセイか何かについて書きたかったけど…今はあまり感情を揺さぶられるお話は読めない。夫の緩和治療のことがあり、日常生活でぐらぐらと感情を揺り動かされているので、小説もエッセイも、ドラマや映画も見たくない。もうお腹いっぱい、という感じ。感情を揺らすための読書ではなくて、落ち着かせるための読書が必要で、普段は読まないHOW TO系の本を手にとって試している。
図書館で真っ黄色の表紙に惹かれて借りたのがこれ。
防犯の基本のき、という内容で特に目新しいものはなかったが、実践的アドバイスが参考になった。子どもに伝えるにはどう話すのがいいか、親子で練習するにはどんなやり方があるかが著者の経験(防犯アドバイザー・コンサル的なお仕事)と共に書かれている。
通学路を歩いてみるとか、スマホの約束事とか、帰宅時間(いわゆる門限)の大切さとか、ごくごく当たり前の防犯対策が具合的にどんな犯罪を防ぐのかが分かるのもよい。基本的なことの徹底と積み重ねが大事なんだとよく分かる。読みやすいので、思春期の子どもには親が言って聞かせるより、自分でこの本を読んでもらうのがいいかも。
価値観が多様化している今、親しいママ友やご近所さんとも考え方がずれる可能性がある。「私の考え方は古いのかな?」「ここまでやるのは過保護かな?」「こんな細かいこと気にしているのは我が家だけ?」「我が家だけあんまり厳しいと子どもが嫌がるかも?」「そんなに大雑把で大丈夫?」「もう少し気にしたほうが…」なんて、みんな内心ドキドキしながら、探り合いながら互いの価値観を擦り合わせているような現状がある。夫婦間でもそうかもしれない。
私の両親は防犯や安全には厳しかった。兄弟が多かったが皆あまり怖い目に合わず、大きな怪我や病気をしないで無事に成長できたのは両親の慎重さのおかげと言える。チャイルドシートなんて一般的でなかった時代にすでに使っていたし、海でも山でもスキーでもしっかり休憩を挟んで決して無理はせず、祖父母や叔父の手を借りて大人の人数を確保して、ととにかく安全最優先だった。
子どもの頃は「もっと海水浴行きたいな」(叔父が帰省しないと行けなかったのであまり気軽なレジャーではなかった)とか「せっかく今楽しいのにもう休憩するの?」とか不満に思うこともあったけど、自分が親になってみると両親の気持ちがよく分かる。体力も判断力も集中力もない子どもを守るためには油断は禁物なのだ。
そんな風に育ったので、私も完全慎重派。この本に書いてある「やったほうがいいよ」ということは大抵履修済み。幸い夫も息子溺愛のため、比較的慎重派。「それは大げさだ」とか「心配しすぎだ」とか言われることはないので助かっている。
ただ、親の安全意識が当の息子にどれだけ伝わっているか、身に着いているか、は大いに不安。
学童に行くようになったり、少しの間ならお留守番するようになったり少しずつ変化(成長?)している中で、怖い目にあったり怪我をしたりしないで済むようにできることはしてあげたい親心。その親心が私の自己満足でなくて息子の実になっているかが問題。この本のアドバイスにならって、「こんな時あなたならどうする?」「なんでそうするの?」と会話しながら確認していこうと思う。
息子が生まれてすぐと昨年の夏と、夫が入院して二人暮らしだった。母子家庭なんて珍しくもなんともない世の中だけど、やはりいろいろな面で心細いもの。身を守る事、家族を守る術は身に着けておきたいところ。